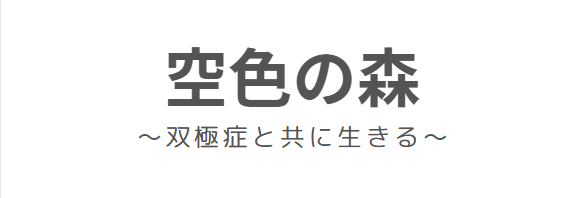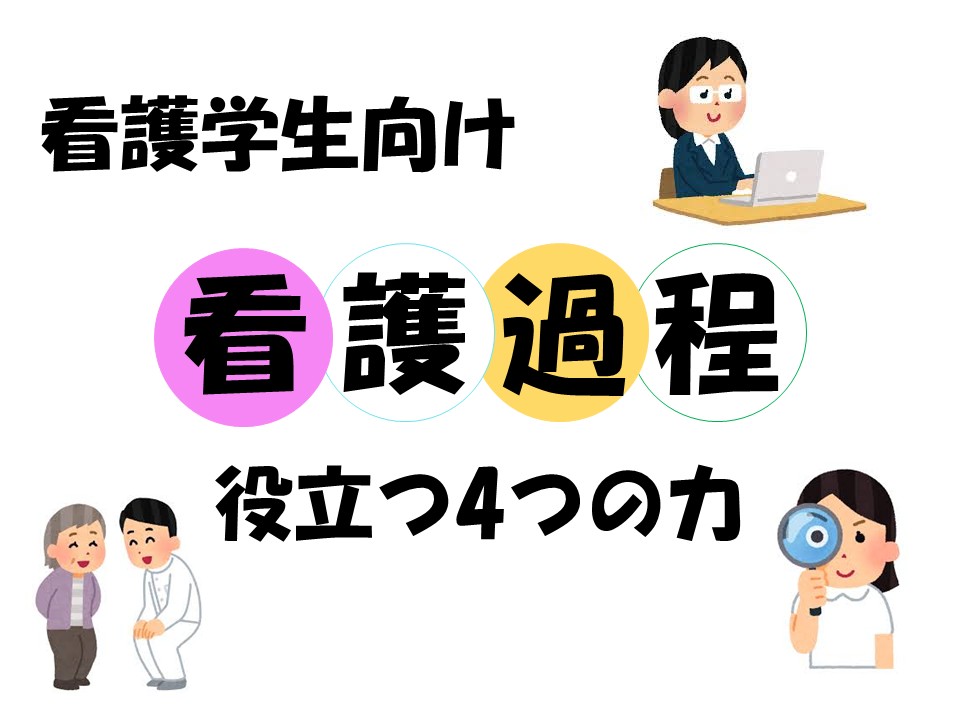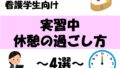この記事は約14分で読めます
こんにちは!空色の森です。
本日は、前回の【看護学生向け】看護過程SOAPの書き方をわかりやすく解説!~アセスメントのコツも紹介~に引き続き、看護過程のお話しとなっています。看護過程を進めるにあたって「こんな力があるといいな」と筆者が感じたものを4つご紹介させていただきます。
最後までお読みいただけますと幸いです(^^♪
看護過程に役立つ5つの力
看護過程については【看護学生】1年生のうちにやっておいた方がいいこと6選と【看護学生向け】看護過程SOAPの書き方をわかりやすく解説!~アセスメントのコツも紹介~でご紹介したとおりになります。
筆者も今まで複数回看護過程を行ってきましたが、そんな中で「こんな力があったらいいな」と思ったものが4つありました↓
1.観察力
2.情報分析力
3.情報検索力
4.計画力
1つずつ見ていきましょう。
観察力
看護過程に役立つ力の1つめは「観察力」です。
看護過程は、S・Oデータを収集するところからスタートします。
Sデータは会話の中で収集できるのですが、Oデータは観察の仕方により質と量が変化していきます。
1人の患者さんを見るときにも、その患者さん自身だけを観察するのか、それともその周り(ベッドや床頭台)まで一緒に観察するのかでは、情報量に差が生まれます。
また、情報量が少ないと正しくアセスメントをすることも難しくなってきてしまいます。
ゆえに、看護過程に役立つ力の1つめは「観察力」とさせていただきました。
観察力は人間観察をすると鍛えることができます。例えば、テレビを見ていて「どうしてこの方はこんな発言をしたのか」「今この方はなにを考えているんだろう」などと芸能人の方を観察しながら推理することを筆者は時々やっています。
情報分析力
看護過程に役立つ力の2つめは「情報分析力」です。
この力は看護過程全体に関わっていく力だなと筆者は感じます。具体的には、①適切な情報選び ②アセスメント ③実施した援助計画の評価に役立ちます。
適切な情報選び
看護過程では最初、S・Oデータの分類からスタートしました。
しかしながら、実際に患者さんと接してみるとSデータもOデータも膨大にあり、全てを情報として取り扱うことは困難です。
その患者さんの困りごとを見極めて解決するために必要な情報を選び取っていく必要があるのです。
アセスメント
アセスメントでは、患者さんやご家族の現在の困りごとを評価していきます。その際に上で分類したS・Oデータを使っていくことになります。
このとき、情報を適切に分析する必要があるのです。例えば、水をあまり飲んでいない患者さんがいるとしたら、そこで終わりにするのではなく水分不足の可能性があることを分析していく必要があります。
実施した援助計画の評価
援助を実施したら、「その援助の手技はどうであったか」、「援助による効果はあったのか」などを分析していく必要があります。
例えば、普段食欲があまりなく半分で食事を終わりにしてしまうAさんがいるとします。Aさんは身体を動かす機会が少ないから食欲がないのではないかと考えた学生は、Aさんと散歩をするという計画を立てました。すると散歩の後の昼食では8割ほどご飯を食べていました。
この事例では、散歩で身体を動かしたことがAさんの食欲につながり、そのことが食事摂取量の増加をもたらしたと考えられます。このように、「情報分析力」は実施した援助計画の評価にも役立ちます。
情報検索力
看護過程に役立つ力の3つめは「情報検索力」です。
看護過程をすすめるにあたり必要となるのが「根拠」です。根拠を探すにあたり「情報検索力」は非常に役立ちます。
根拠に用いる情報は科学的な裏付けが必要となります。すなわち、信頼性の高い情報を使用しなければなりません。これは、不確実な根拠を基に実施したアセスメントや援助が患者さんに不利益をもたらさないようにするためです。
そうなると、書籍や論文からの情報が好ましいと筆者は考えます。書籍や論文から自分の欲しい情報を引き出すには少しコツが必要となりますので、時間のある内に練習しておくことをおすすめします。
情報検索力は、何か調べたいことがあったときに図書室の本を利用するようにすると身についてくるかと思います。また、キーワードの選定も大切になってきます。
目星の本が見つかったら必ず索引ページから探すようにしましょう!本の頭から探すのとは要する時間が全く変わってきますのでぜひ覚えておいていただけると嬉しいです。
計画力
看護過程に役立つ力の4つめは「計画力」です。
これはSOAPのPでとても役に立ちます。必要な計画力は主に2つに分けられると筆者は思います。
患者さんの個別性に合わせた計画を立てる力
計画を立てる際に大切なことは、患者さんの個別性に合わせることです。
例えば患者さんの価値観に全く合わない計画を立ててしまうと、関係性が壊れてしまう可能性があります。
他にも患者さんの持つ力を超えた計画を立ててしまうと実施が困難となってしまいます(例:両足骨折している人のトイレ誘導など←極端ですが…(;´∀`))
ですので、患者さんの個別性に合わせた計画を立てる「計画力」が看護過程では役立つと筆者は思います。
目標達成日から逆算してスモールステップで計画を立てる力
計画は目標を達成する日から逆算して考えていく必要があります。例えば急性期ですと退院日や計画の中間評価日がそこにあたります。
ですが、いきなり大きな目標を達成することは難しいです。(ダイエットでも1週間で5kg痩せるという目標は無謀ですよね(゜o゜))
ですので、目標達成日から逆算して小さい目標(スモールステップ)を1つずつ達成し、最終的に大きな目標が達成できるように計画を立てていく必要があります。
ダイエットを例にすると、大きな目標が「夏までに5kg痩せる」だとしたら、「〇/〇まで毎日腹筋を15回行う」「〇/〇まで毎朝野菜を食べる」という小さい目標を立てます。これが達成できたら次は「□/□まで毎日腹筋を30回行う」「□/□まで毎食野菜を食べる」という風に目標を少しレベルアップしていきます。この日付を考える際には、大きな目標を達成する日を考慮し、逆算するようにしましょう。
以上から、看護過程で役立つ力の5つめとして「計画力」を挙げさせていただきました。
最後に
いかがでしたでしょうか。最後にもう1度まとめさせていただきます。
看護過程で役に立つ力
1.観察力
2.情報分析力
3.情報検索力
4.計画力
これらはあくまでも筆者の主観ですので、当てはまらない部分もあるかもしれませんが、参考にしていただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)