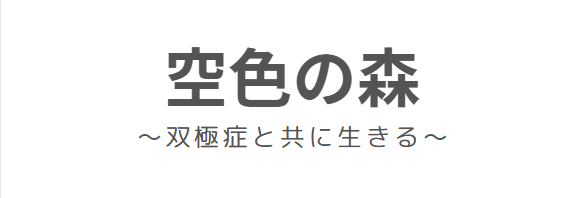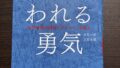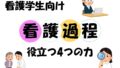この記事は約16分で読めます
こんにちは!空色の森です。
今回は看護過程をテーマにした記事を書かせていただきます。筆者自身がまだ看護師として働いているわけではないので、最初は記事にしてよいか悩みました。しかし、自分が1年生だったころにこんな記事があったら良かったなという思いから、今回投稿することにいたしました。
拙い文章になるかもしれませんが、最後までお読みいただけますと幸いです(^^♪
看護過程とは

看護過程とは何ですか?

看護をする前に「どうして何のためにどんな看護をするのか」「実際に援助したらどのように患者さんは変化したのか」「ではそれを踏まえて次はどうするのか」について繰り返し考えることだよ。
看護過程の概要については【看護学生】1年生のうちにやっておいた方がいいこと6選でご紹介したとおりとなります。今回はこれをより詳しく説明していきますね(^^)/
看護過程はSOAPで行われることが多いです。SOAPがそれぞれ何を指すのかは以下のとおりです↓

では、筆者の例を使って一緒に看護過程を行っていきましょう!
※便秘がテーマとなります。
SO(SデータとOデータ)
今回の例は母と筆者のやり取りを用いていますが、わかりにくいのでAさんとBさんにします。

(うーん、今日も出なかった。これで3日目だよ。なんか気持ち悪いし…
全然勉強に集中できないや)

(Aさんどうしたのかな、なんか顔色が悪いし、冷や汗も出てる)
Aさんどうしたの?具合が悪そうだよ

実は3日間出てないんだよね…。前は毎日出ていたのに。

それは辛いね…。ご飯とかちゃんと食べられてる?

うん。一昨日はポテト、昨日はスパゲッティを食べたよ!でも、さすがに今日は食欲がないかな…。朝ごはんも食べていないし。

(そういえば最近野菜食べてるところみてないな)そっかあ。そういえば最近運動してる?(前は頑張ってたけど最近運動しているところ見てないな…)

それができてないんだよ。前は筋トレとかしてたんだけど、なんか面倒くさくなちゃって…疲れるし。

気持ちはわかるよ。でもどうにか治したいね…
やりとりはここまでになります。では、これをSデータとOデータに分けてみましょう。
Sデータとは主観的な情報を指します。すなわち、患者さんやご家族が言ったこと・感じたこと=援助者が患者さんやご家族から聞いたことです。
上の会話でいうとAさんの吹き出しから出ている言葉はすべてSデータとなります。(1つめの吹き出しは心の声なので除きます。)
Sデータを書く際は勝手に内容を変えたり、省略したりしないように注意しましょう。
一方、Oデータは客観的な情報を指します。すなわち、援助者が観察したことやバイタルサイン測定・検査などから得られた値のことです。
上の会話でいうとBさんの吹き出しから出ている言葉のうち、( )の中に入っているものがOデータとなります。
では、まとめてみましょう。
Sデータ(主観的情報)
・援助者が患者さんやご家族から聞いたこと
・勝手に内容を変えたり、省略したりしない
Oデータ(客観的情報)
・援助者が観察したことやバイタルサイン測定・検査などから得られた値(+援助したこと)
・内容が変わらなければ言葉は変えてもよい
例)爪と口唇が青紫色→チアノーゼがみられる
なので、上の会話からS・Oデータを書き出すと以下のようになります。
Sデータ(主観的情報)
・実は3日間出てないんだよね…。前は毎日出ていたのに。
・一昨日はポテト、昨日はスパゲッティを食べたよ!でも、さすがに今日は食欲がないかな…。 朝ごはんも食べていないし。
・それができてないんだよ。前は筋トレとかしてたんだけど、なんか面倒くさくなちゃって…疲れるし。
Oデータ(客観的情報)
・顔色不良、冷や汗あり(なんか顔色が悪いし、冷や汗も出てる)
・野菜の摂取量が以前より減少(そういえば最近野菜食べてるところみてないな)
・運動量が以前より減少(前は頑張ってたけど最近運動しているところ見てないな…)
A(評価、アセスメント)
続いては、SOAPの「A」である「評価=アセスメント」をしていきます。なぜなら、S・Oデータのみだと、今患者さんやご家族に何が起こっていて、何に困っているのかが明確にならず、援助の計画を立てられないからです。
では、今Aさんが何に困っているのか考えてみましょう。
おそらく「3日間排便がないこと=便秘傾向」ですね。
この「おそらく」の部分をS・Oデータを使ってはっきりさせていき、また今後どうしていくのか方針を立てるところまでがアセスメントとなります。
では、まとめてみましょう。
A(評価、アセスメント)
・今の問題をS・Oデータを使って明確にする
・今後の方針をS・Oデータを使ってたてる
なので、現在のAさんの状態をアセスメントすると以下のようになります。
Aさんは3日間排便がない。一般的に排便は1日1~2回あることが正常であり、Aさんは以前毎日排便があった。現在は排便がなく、食欲も低下しており日常生活へ支障をきたしていることから便秘傾向であると考える。原因としては食物繊維および運動の不足が考えられるため、そこを援助していく必要がある。
↓さらに要約すると
3日間排便がなく食欲低下しており便秘傾向。以前は毎日排便があった。食生活の改善と運動習慣の確立を促す必要あり。
P(計画)
アセスメントが終了したら次は「P」である「計画」に移っていきます。計画では、アセスメントで立てた方針に従い具体的なものを書いていきます。例えば、口腔ケアの実施とか食事介助などです。
では、まとめてみましょう。
P(計画)
・アセスメントで立てた今後の方針に従って具体的な計画を立てる
なので、例えにはなりますが現在のAさんの計画を立てると以下のようになります。
食物繊維の摂取を促す。日々の運動を促す。
最後に
いかがでしたでしょうか。では、最後にもう1度まとめさせていただきます。
Sデータ(主観的情報)
・援助者が患者さんやご家族から聞いたこと
・勝手に内容を変えたり、省略したりしない
Oデータ(客観的情報)
・援助者が観察したことやバイタルサイン測定・検査などから得られた値(+援助したこと)
・内容が変わらなければ言葉は変えてもよい
例)爪と口唇が青紫色→チアノーゼがみられる
A(評価、アセスメント)
・今の問題をS・Oデータを使って明確にする
・今後の方針をS・Oデータを使ってたてる
P(計画)
・アセスメントで立てた今後の方針に従って具体的な計画を立てる
この後は、Pで立てた計画をより詳細に考えて実施していきます。例えば、日々の運動を促すなら「一緒に運動する」「運動する時間を決める」などです。
実施内容はOデータ(O)となり、また実施中の患者さんやご家族の発言はSデータ(S)となります。これを基に援助内容が適切であったか、再びアセスメント(A)し、計画(P)を修正していくという繰り返しになります。
本ページの説明が皆様の看護過程の一助になりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)