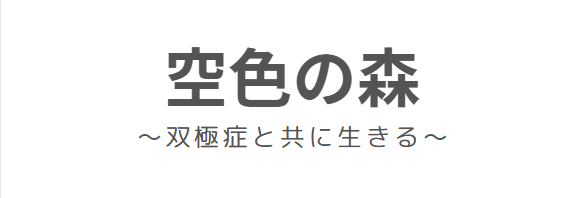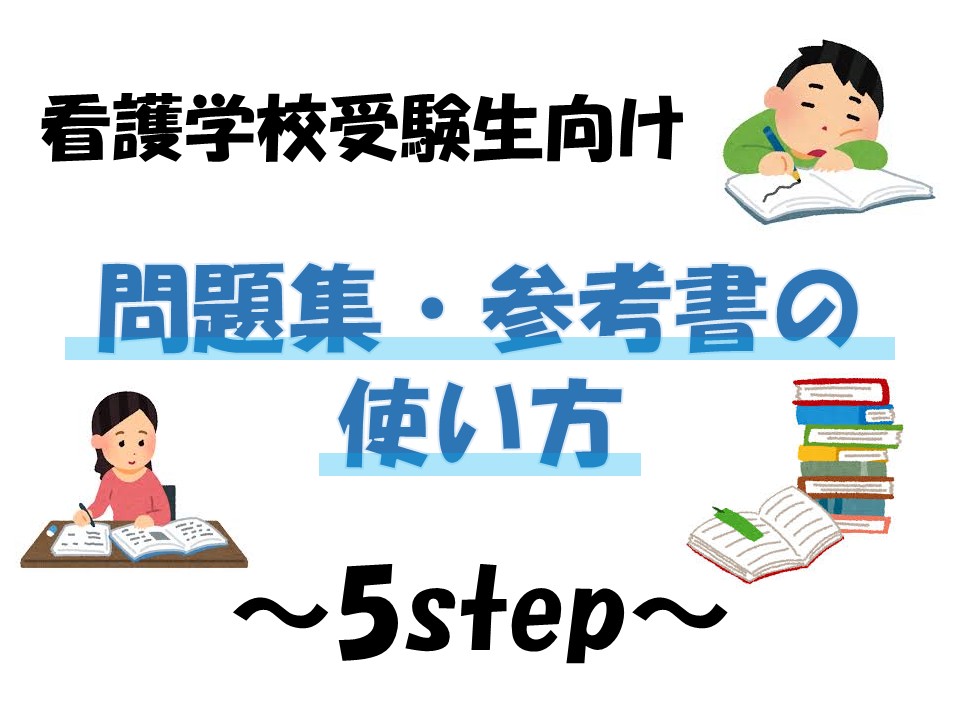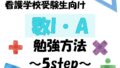この記事は約10分で読めます
こんにちは!空色の森です。
新学年に入り、新高校3年生は「志望校合格に向けて勉強を始めなきゃなぁ」と考え始める時期ですね。
筆者は当時問題集を買ったはよいものの、どんな風に勉強すればよいのかわからず色々と試行錯誤していた時期がありました。
本記事ではそんな試行錯誤の末、導き出した受験問題集・参考書の使い方を5stepでご紹介していければと思います。
最後までお読みいただけますと幸いです(^^♪
受験問題集・参考書の使い方~5step~
問題集の効率的な使い方は以下のとおりです↓
問題集の使い方
1.問題を自力で解く(3~5分考えて解き方が思い浮かばなかったら解答を見る)
↓
2.丸付けをする
↓
3.間違えていれば解説を読んで、実際に解答を書き写す
何も見ないでもう1度解いてみる
間違えた問題のページに付箋を貼っておく
↓
4.次の問題を解く
↓
5.全部解き終わったら付箋のついた問題を解く(正解したら付箋を外す)
付箋がなくなるまで周回する
それでは、1つずつ解説していきたいと思います(`・ω・´)
step1 問題を自力で解く

step1は、「問題を自力で解く」です。
このときのポイントは
3~5分考えて解き方が思い浮かばなかったら解答を見る
です。
理由は、何分、何十分も自分で考えるよりも、解答を見て解き方を身に付けた方が効率が良いからです。考えることはとても大切なことであると筆者は思います。
しかし、受験勉強は時間との勝負でもあるので、ここは解答冊子を最大限に活用していきましょう!!
step2 丸付けをする

step2は、「丸付けをする」です。
ここでのポイントは
答えが合っていたときにも解答に目を通す
です。
特に数学がそうなのですが、自分が解き方とは他の方法で参考書が解いていることがあります。さらに、その解き方が自分の解答方法よりも効率が良いことがあります。
解き方のパターンを増やすためにも解答には必ず目を通しましょう。
step3 間違えていた時の対処法
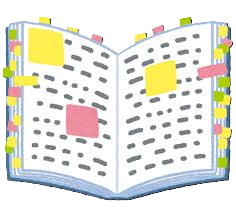
step3は、「間違えていた時の対処法」です。
まずは解説を読んで実際に書き写します。書き写すことで、解答の流れを身に付けることができるからです。
続いて、何も見ないでもう1度解いてみます。←ポイント
人間の記憶は覚えた瞬間から忘れていきます(エビングハウスの忘却曲線)。ですので、解答方法を覚えたらすぐに復習することが大切です。
最後に、間違えた問題の箇所に付箋を貼っておきます。これはstep5で使用します。
step4 次の問題を解く
step4は、「次の問題を解く」です。
ここから先はstep1~3をひたすら繰り返し、最後の問題まで解いていきます。
一番大変なところですが、頑張っていきましょう!
筆者は1日に解く問題をあらかじめ決めていました!
もちろん、終わったらお菓子を食べるなどのご褒美付きです♪(*´▽`*)
step5 付箋のついた問題を解く

step5は、「付箋のついた問題を解く」です。
step3では、間違えた問題に付箋を貼っていきました。ここでは、その間違えた問題のみを解いていきます。理由は1回目で解けた問題はおそらくこれから先も自力で解けると思うからです。
付箋のついた問題が何も見ないで解けた場合には、付箋を外します。解けなかった場合には、付箋はそのままにし、☆マークをつけておきましょう。
このあとは、付箋がなくなるまでひたすら周回します。
このとき、繰り返し間違えた問題には星マークが増えていくと思うので、もし後々同じ問題集を使用する場合にはこの☆マークを優先して解いていきましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。もう1度まとめさせていただきます↓
問題集の使い方
1.問題を自力で解く(3~5分考えて解き方が思い浮かばなかったら解答を見る)
↓
2.丸付けをする
答えが合っていたとしても解答には目を通す
↓
3.間違えていれば解説を読んで、実際に解答を書き写す
何も見ないでもう1度解いてみる
間違えた問題のページに付箋を貼っておく
↓
4.次の問題を解く
step1~3を繰り返す
↓
5.全部解き終わったら付箋のついた問題を解く(正解したら付箋を外す)
付箋がなくなるまで周回する
間違えた問題には☆マークを付ける
本記事が皆様の勉強の一助となりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)